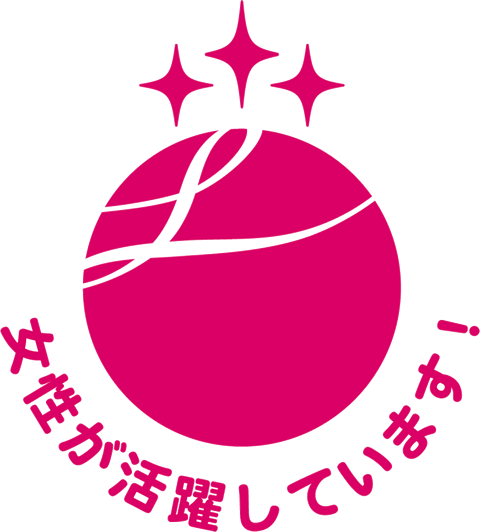厚生労働省より令和6年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
ここ数年、社会環境の変化もあり、男性の育児休業の取得率が急上昇しています。
男性 40.5%(前年30.1%)
女性 86.6%(前年84.1%)
下記HPに記載があるグラフをご覧いただければ分かる通り、女性はここ20年くらいの間、ほぼ8割台で推移していますが、男性は平成29年度に初めて5%を超え、上昇ペースが強まり、ここ2年間で急増という状況になっています。
厚生労働省より令和6年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
ここ数年、社会環境の変化もあり、男性の育児休業の取得率が急上昇しています。
男性 40.5%(前年30.1%)
女性 86.6%(前年84.1%)
下記HPに記載があるグラフをご覧いただければ分かる通り、女性はここ20年くらいの間、ほぼ8割台で推移していますが、男性は平成29年度に初めて5%を超え、上昇ペースが強まり、ここ2年間で急増という状況になっています。
基本手当日額に関し、2025年8月1日より以下のとおり変更となることが厚労省より先日公表されました。
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
(2)45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
(3)30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
(4)30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,295円 → 2,411円(+116円)
これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額も変更になります。
厚生労働省から就労条件総合調査の令和6年の結果が公表されました。その中で週休制に注目してみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 90.9%で、令和5年調査 85.4%よりも、5.5ポイント増えています。また「完全週休2日制」を採用している企業割合は 56.7%で、こちらも、令和5年調査 53.3%から3.4ポイント増えています。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
障害者雇用促進法では、事業主に対し、法定雇用率である2.5%(民間企業の場合)以上の障害者を雇うことを義務付けていますが、厚生労働省は昨年末、実際の雇用状況についてまとめた令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。これによれば、民間企業の障害者実雇用率が過去最高「2.41%」を更新してしました。集計結果に関しては、以下URLをご参照ください。
2024年12月2日から、現行の健康保険証は新規発行されなくなり、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードを健康保険証として利用するいわゆる「マイナ保険証」の運用が本格的になります。合わせてマイナンバーカードを持っていない人等、マイナ保険証を利用できない人に対して、資格確認書の発行等も始まります。
協会けんぽではこれに際し、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関する問い合わせを受け付ける「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を設置しています。日本語のみでなく、英語・中国語・韓国語をはじめとした22か国語での対応も行われています。
厚生労働省から2024年(令和6年)夏季一時金妥結状況の調査結果が公表されました。これによれば、2024年夏季一時金の平均妥結額は過去最高の898,754円で、昨年と比較して53,197円(6.29%)のプラスとなっています。業種別で対前年比を見ると、紙・パルプ、電力・ガス、サービスで2桁の伸びとなっています。
先日、「令和6年版 労働経済の分析」が厚生労働省より公表されました。労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回の白書では「人手不足への対応」がテーマとなっています。第Ⅰ部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられており、第Ⅱ部では、現在の日本の人手不足の動向やその背景を分析し、人手不足への対応に向けた方向性等を示しています。
厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインの内容を分かりやすくまとめたリーフレットでは、「ガイドラインの基本的な考え方」、個人事業者等に対して「自身で実施していただきたい事項」、注文者等に対して「注文者等として実施していただきたい事項」などが記載されています。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40367.html
厚生労働省は、このたびワークシートと特設サイトから成る年金教育教材を新たに公開しました。難解と思われがちな年金制度を理解しやすい教材となっています。
2024年4月より、求人募集を行う際の労働条件の明示についての明示事項が追加となります。これに関するQ&Aが厚生労働省から公表されました。求人募集がスムーズに行える様になるよう、参考にしてください。
厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。先日、この年報の令和4年版が公開されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、年間171,528件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が142,611件(全体の83.1%)となっています。
そして、この「定期監督等」の違反状況について、件数の多い上位3位は以下の通りです。
1位 労働安全衛生法66条~66条の6(健康診断) 29,974件
2位 労働安全衛生法20~25条(安全基準) 27,041件
3位 労働基準法32条(労働時間) 22,305件
その他の詳細は下記URLをご参照ください。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r04.pdf
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しており、12月5日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、カスタマーハラスメントがとり上げられる予定です。
カスタマーハラスメントに関しては、2023年9月1日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正における「業務による心理的負荷評価表の見直し」において、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されるなど注目が集まっており、企業としての対策も重要になっています。
今回、3つのリーフレット(職場のハラスメント、カスハラ、就活ハラスメント)が公開されていますので、社内研修に活用するなどして、未然に防止する取組みをしていきましょう。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html
カスタマーハラスメントリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168047.pdf
2024年4月1日からは、労働条件の明示事項が追加され、建設業やの運送業、医師に対して適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が適用となります。これらの変更に伴い従業員に対して示す様式や役所に対して届け出る様式も変更されます。この件につき厚生労働省から、労働基準法等関係主要様式の主要様式ダウンロードコーナーで新しい様式が公開され、準備が進められるようになりました。
厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
年収の壁対応策として公表された複数のメニューのうち、新たに社会保険に加入したパートタイマー等に対する企業への助成金として、キャリアアップ助成金の新コースが設けられました。制度が複雑であり、なかなか全体像を理解することが難しいものになっていることもあり、厚生労働省が制度の解説をした動画の公開をしましたのでご参考ください。
見出し
厚労省より2022年度の男性育休取得率の調査結果が公表されました。調査結果によると、2022年度の男性の育休取得率は「17.13%」となり、2021年度の13.97%から微増しました。なお、女性の育休取得率は80.2%(2021年度 85.1%)となっています。男性の育休取得率は微増ながら年々増加傾向にあり、育児・介護休業法の改正の効果が少しずつ現れてきているのかもしれません。
厚労省より「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果が公表されました。今回の調査において「メンタルヘルス不調による休業者」に関しての調査結果の記載がありました。過去1年間(2021年11月1日から2022年10月31日)にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は13.3%(前年調査10.1%)となっています。このうち、連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.6%(前年調査8.8%)、退職した労働者がいた事業所の割合は5.9%(前年調査4.1%)でした。
働き方改革の中で創設された高度プロフェッショナル制度(2019年4月1日施行)に関して、厚労省が最新(令和5年3月末時点)の対象労働者数を公表しました。結果として、26事業場(24社)/823人しか制度が適用されていないことが分かりました。この理由について、基準が厳しすぎるからという意見が挙がっています。もっとも近年は管理監督者でなくとも、高額の報酬を得る社員も増えていますし、イノベーションが必要な業務が増加するのは確実な状況ので、今後、徐々に適用者が増えてくるのかも知れません。
2023年3月に「厚生労働省 委託事業 令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」の企業調査結果が公表され、育児短時間勤務の1日の設定勤務時間の割合が公表されました。
この企業調査の結果をみると以下のようになっています。
4時間以内 4.7%
4時間超5時間以内 6.5%
5時間超6時間以内 10.3%
6時間 68.0%
6時間超7時間以内 22.1%
7時間超8時間以内 9.2%
日によって異なる 9.9%
週休3日制度等短日数勤務のため、1日あたりは通常の勤務と同じ 1.4%
育児・介護休業法で義務付けられている「原則 6時間」よりも短い時間数がある一方で、「6時間超7時間以内」が2割を超え、「7時間超8時間以内」が1割弱となっています。少しでも長い時間を勤務してもらうことで、人材不足の解消につながっていくことが期待されます。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html
日本・オーストリア両国政府は、2022年9月から「日・オーストリア社会保障協定」の締結に向けた政府間交渉を進めてきましたが、その結果、実質合意に至ったと厚生労働省より発表がありました。今後、両国は、本協定の署名に向けた協定案文の確定等の必要な作業及び調整を行います。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/houdounenkin_20230513_00001.html
近年、企業に雇用されず、フリーランスとして働く方が増えていることを背景に2023年4月28日の参議院本会議で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しました。
この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)の取引について、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとされています。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html