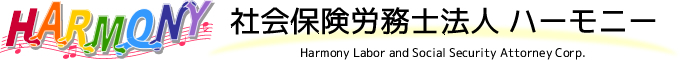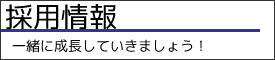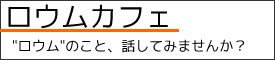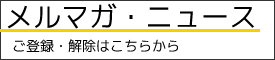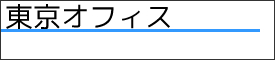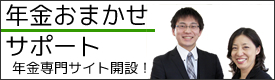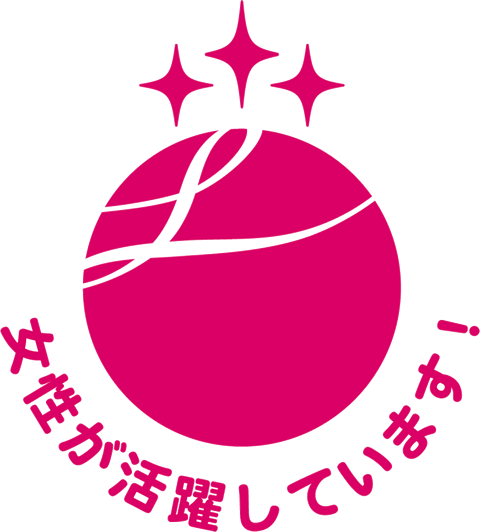副業・兼業の促進に関するガイドラインおよびQ&A
厚労省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が公開されています。
それに合わせて、副業・兼業に関するQ&Aも公開されおり、「情報公開」についても以下のような内容が公表されています。
・4−1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。
・4−2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
・4−3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
・4−4 グループ企業で一体として公表することは可能か。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」7月8日改定版
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
Q&A